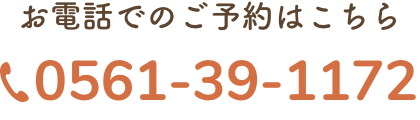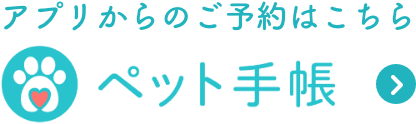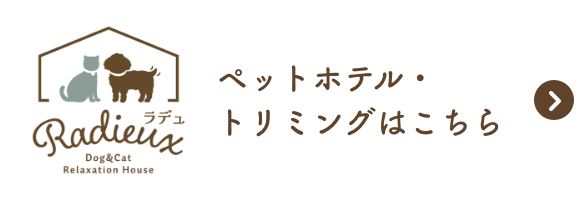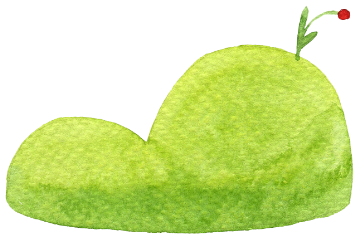猫の病気
2025.08.05
猫の歯肉口内炎
猫の歯肉口内炎とは
歯肉のみならず、口腔粘膜、特に口の奥の尾側粘膜にまで及ぶ炎症や潰瘍、肉芽組織の増殖を起こす難治性の病気です。別名尾側口内炎とも呼ばれます。

正常の猫の口腔内

当院での症例

上記の症例と同じ
猫の歯肉口内炎の原因
口腔内の細菌やウイルス、免疫反応の異常などの複数の要因が関わっていると考えられていますが、発症原因には不明な点が多いと言われています。
猫の歯肉口内炎の症状
主な症状としては、食欲の低下、元気消失、口の中の強い痛み、ウエットフードを好んで食べるようになる、体重減少、よだれが多い、口臭、毛づくろいをしなくなったなどが挙げられます。
また、血液交じりの唾液、下顎リンパ節の腫大なども認められます。
猫の歯肉口内炎の診断
猫の場合、歯周病や歯の吸収病巣(歯が溶けていく病気)を伴っていることが多いので、麻酔をかけた時に歯科用レントゲンを撮影し、最終判断を行います。肉芽組織の増殖が生じている場合は、腫瘍性疾患の可能性もありますので、病理組織検査をすることもあります。
猫の歯肉口内炎の治療
第一選択は外科治療による抜歯です。口腔内細菌の清浄化をする必要があるため、まずは全臼歯抜歯(切歯・犬歯以外の歯の全抜歯)を行います。全臼歯抜歯で80%の治癒が期待でき、改善がない場合は、全顎抜歯(残りの切歯・犬歯の抜歯)を行います。全顎抜歯により90%以上の治癒が期待できます。
内科治療としては、抗生剤やステロイド剤を使用します。しかし、抗生剤の効果は一時的であり、長期使用をすると耐性菌を生み出してしまうリスクもあります。ステロイドは内科治療の中では最も効果的ですが、長期使用による副作用には注意が必要です。内科療法では基本根治は望めず、長期的に使用せざるを得ません。また、ステロイドを投与していた子では、抜歯を行っても口腔粘膜の炎症が治癒しにくいことがわかってきていますので、できる限り早期の抜歯治療が推奨されています。

上の写真は上記の症例で全臼歯抜歯2カ月後です。粘膜の発赤の範囲は縮小傾向、肉芽組織の腫脹はなくなり、食欲がもどりました。治癒が早い子は抜歯後3~4カ月ほどで口腔粘膜の発赤がほとんど目立たなくなります。
食欲の低下、カリカリを食べなくなった、口を気にすることが多い、よだれがでるようになった猫ちゃんは愛知県東郷町 なぐら動物病院までご相談ください。
獣医師 安部昌平